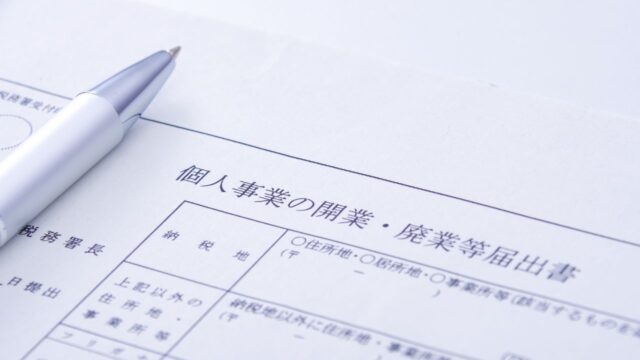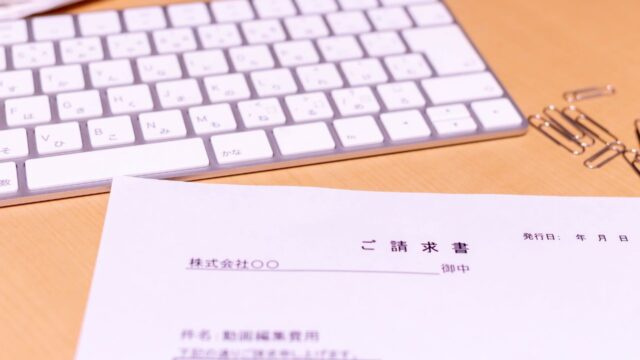フリーランスや個人事業主には、会社員のような「年末調整」はありません。自分が営む事業に対し、利益や税金を計算し、毎年申告する必要があります。ここではフリーランスになったばかりの人にもわかりやすく、簡単な確定申告のやり方について解説します。
フリーランス・個人事業主の確定申告とは?
確定申告は、簡単に言いますと「1年間の収入と支出、利益を記載した書類を提出し、納税額を確定させるための作業」です。
サラリーマンのような給与所得者からフリーランス・個人事業主になった人が、まず戸惑うのが確定申告ではないでしょうか。
サラリーマンの場合、毎月源泉徴収が行われ、所得税を納めています。しかし、中には払い過ぎとなっていることがあり、ここで払い過ぎた税金を取り戻す作業が「年末調整」です。年末調整は、会社がほとんどの作業を担当してくれるため、個人が特別にやるべきことはありません。しかし、フリーランスの場合は、もちろん自分でやらなければいけません。
一見難しそうですが、一度理解すれば簡単です。ここからは、順を追って確定申告のやり方をチェックしていきましょう。
フリーランスにも確定申告が必要なケース・不要なケースがある
実は、フリーランス=絶対に確定申告が必要というわけではありません。まずは自分がどちらに当てはまるのか、確認しましょう。
その前に、理解しておきたいのが「事業収入」「事業所得」の考え方です。
事業所得とは、事業収入から必要経費を引いたものをいいます。確定申告は、所得税を申告するために必要なものです。つまり所得が一定以下の場合、行う必要がありません。
事業所得=事業収入―必要経費
課税所得額=事業所得―所得控除(基礎控除や配偶者控除など)
上記の式に1年間の収入と必要経費を当てはめ、事業所得を計算しておきましょう。所得控除の額は、個人により異なります。
(例)
基礎控除:48万円
配偶者控除:(一般):13〜38万円
社会保険料控除:国民年金保険料、国民健康保険の保険料など
生命保険料控除:生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料(一定の金額が控除)
所得税の計算には、所得税の速算表を使用します。
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
上記の表と次の式を利用すれば、所得税額と納める所得税が計算できます。
課税所得額×所得税率-控除額=所得税額
所得税額―税額控除額=納める所得税
(例)フリーランスのAさん
事業収入300万
必要経費50万
基礎控除48万
社会保険料控除40万
税額控除0円
300万―50万=250万(事業所得)
250万―(48万+40万)=162万(課税所得額)
162万×5%=81,000円
Aさんが収める所得税は81,000円です。このように、一度自分の課税所得額と所得税を計算してみましょう。
確定申告が必要なフリーランスとは
一定以上の事業収入がある
フリーランスの仕事をメインとして一定の所得がある場合は、確定申告が必要です。課税所得額に対して所得税が発生するため、赤字の場合や所得よりも所得控除が多い場合を除き、確定申告が必要だと考えておきましょう。
本業以外の収入がある
フリーランスとして働きながらアルバイトをしている、フリーランスの傍ら株や投資信託、FXをしているといった場合は、確定申告が必要となるケースがあります。
フリーランスの事業収入+アルバイト1ヵ所
→アルバイト先で年末調整。事業収入が20万円を超える場合確定申告が必要
フリーランスの事業収入+アルバイト2ヵ所以上
→アルバイト先1ヵ所で年末調整。残りのアルバイト収入+事業収入が20万円を超える場合確定申告が必要
また株式やFXで得た利益は、原則として確定申告が必要です。
確定申告をしなくてもいいフリーランスとは
本業の利益が赤字や基礎控除の48万円を下回る場合は、所得税が発生しないため、確定申告は不要です。
48万円を超えていたとしても、社会保険料控除や生命保険料控除など、そのほかの控除により、「事業所得<所得控除」となるケースも考えられます。この場合も確定申告は不要です。
ただし、青色申告制度を利用し、翌年以降に赤字を持ち越したい場合は、確定申告をする必要がある点に注意しましょう。
確定申告「青色申告」「白色申告」の違いを知ろう
個人事業主の確定申告には、3種類あります。
・青色申告(65万控除)
・青色申告(10万控除)
・白色申告
青色申告をするための条件
・税務署へ開業届を提出
・税務署へ「青色申告承認申請書」を提出
どちらもその年の3月15日までに提出する必要があります。
青色申告のメリット・デメリット
メリット1:青色申告特別控除がある
青色申告では特別控除を受けることができます。e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行った場合の控除額は65万円です。電子申告や電子帳簿保存を行わない場合は55万円控除、簡易(単式)簿記で取引記録を保存する場合は10万円控除です。
青色申告=65万円控除ではなく、条件ごとに控除額が違う点に注意が必要です。
メリット2:家族に払う給与を経費にできる
配偶者や親、子どもなど、生計を同一とする家族に支払う給与を「専従者給与」といいます。白色申告の場合、経費にできる給与には上限があります。しかし、青色申告の場合、上限は決められていません。
※その年の3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
メリット3.:3年間、赤字の繰越ができる
事業は、毎年黒字が続くとは限りません。利益が出た年もあれば、赤字の年もあることでしょう。しかし、青色申告の場合、3年間赤字の繰越が可能です。
(例)
1年目:赤字100万円
2年目:赤字50万
3年目:事業所得200万
赤字の繰越をしていない場合。事業所得200万円に対して所得税を支払う必要があります。しかし、赤字の繰越をしていた場合、3年目の事業所得は50万として計算されるため、節税につながります。
メリット4:「家事按分」の制度が利用できる
フリーランスの場合、自宅で仕事をするケースも考えられます。家賃、電気代、インターネット料金などは、事業で使用する分もあれば、プライベートで使用する分もあります。「家事按分」の制度を使うことで事業として使用した分のみ、必要経費として計上することが可能です。
※家事按分の制度を使うためには、合理的な説明が必要です。例えば、家賃10万円、面積の30%が仕事部屋のため、3万円を経費として申告する、など。
白色申告の場合でも、家事按分の制度を使うことはできます。ただし、業務に関連する割合が50%以上または明らかに区分できるなどのルールを満たす必要があります。家賃やパソコン、自動車など、事業とプライベートを明確に分けにくいものを使用し事業をしている人は、青色申告を利用することをおすすめします。
デメリット1:事前準備が必要
その年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を出さなければ、青色申告をすることができません。もし、年度途中で開業した場合は、開業から2ヵ月以内に出す必要があります。開業届を出す際に、青色申告にするかどうかを決めておき、同時に出しておくことをおすすめします。
デメリット2:複式簿記での記帳が必要(ただし会計ソフトを使えば便利)
青色申告で65万円(または55万円)の特別控除を受けたい場合、複式簿記での記帳が必要です。簿記の知識がない人にとっては、やや難易度が高くなります。
しかし、会計ソフトを使用すれば、それほど手間はかかりません。サブスクで利用できるサービスもあり、不明点もチャットやメール、加入によっては電話で質問することができます。
私も会計ソフトfreeeを使用していますが、とても便利です。
デメリット3.:毎年確定申告の義務がある
青色申告の場合は、毎年確定申告をする義務があります。赤字を繰り越せる点はメリットですが、収入が少ない年が続く人にとってはデメリットと感じるかもしれません。
※「所得税の青色申告承認申請書」の提出は1回のみです。毎年新たに提出する必要はありません。
白色申告のメリット・デメリット
メリット1:青色申告のような開始手続きが不要
白色申告の場合、青色申告のような税務署への事前手続きは必要ありません。思い立った年からすぐに始めることができます。
メリット2:記帳がカンタン(青色申告と比べて)
白色申告の場合、簡易簿記での記帳が認められています。青色申告と比べるとカンタンかつ確定申告時の入力項目も少なめです。
デメリット1:特別控除が受けられない上、帳簿つけが義務化
以前の白色申告は帳簿づけと書類の保存が不要な点が大きなメリットとしてあげられていました。しかし、平成26年以降、白色申告でも記帳義務が課せられています。
つまり、現在では次のような状態になっています。
| 青色申告 (65万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | 白色申告 |
| 複式簿記 | 簡易(単式)簿記 | 簡易(単式)簿記 |
厳密には、確定申告時の提出書類による違いがあるものの、青色申告10万円控除と白色申告の控除なしであっても、同じ簡易簿記での帳簿つけが必要です。
帳簿つけが必須ならば、青色申告の10万円控除を利用した方がお得です。
デメリット2:3年間の赤字繰越制度が使えない
白色申告には、赤字繰越制度はありません。赤字と黒字を繰り返している事業者や赤字が数年単位で続き、黒字に転換できた場合などは、青色申告者以上に所得税を払わなければいけないケースも考えられます。
フリーランスが経費にできるもの・できないもの
経費とは、事業に関連する費用です。事業内容により、経費にできるもの・できないものは異なりますが、ここでは一例として紹介します。
フリーランスが経費にできるもの
| 消耗品費 | ボールペンやメモ帳、コピー用紙などの事務用品など(10万円以内) |
| 旅費交通費 | 取引先に向かうための電車代、バス代、タクシー代など |
| 接待交際費 | 取引先との会食、お歳暮、お中元など |
| 租税公課 | 固定資産税、自動車税、個人事業税など |
| 通信費 | 事業用の携帯電話代、固定電話代、切手代など |
| 広告宣伝費 | 名刺、パンフレット制作、SNS広告費など |
個人事業主のフリーランスの場合、自宅兼事務所として使用するケースも多いです。こういった場合は、家賃や光熱費(電気代、水道代など)も、事業分に限り経費として計上が可能です。
注意しておきたい経費にできないもの
事業と無関係なものは、もちろん経費にはできません。しかし、他にも経費にできないものがあります。間違えやすい内容について解説しておきます。
所得税、住民税
経費として計上できる内容の中に「租税公課」がありました。しかし、同じ税金でも所得税や住民税は、事業には関係がなく、個人(事業主)が支払う税金です。そのほか、相続税や贈与税も経費計上はできません。
罰金
取引先に向かう際に、交通違反などをして反則金・罰金を支払った場合でも、罰金は経費計上できません。所得税や住民税と同じく個人(事業主)が支払うものだからです。
健康診断、人間ドックの費用
会社の場合、従業員の健康診断は義務であり、経費としての計上が可能です。しかし、フリーランスの場合、本人の健康診断費は経費計上できません。人間ドックの費用についても同様です。
福利厚生費
そもそも福利厚生費とは「事業主が従業員のために支払ったサービスの費用の中で必要と認められた経費」です。慶弔見舞金や条件を満たす社員旅行費用、外部の福利厚生施設(スポーツクラブなど)の利用費用などが挙げられます。
事業主が従業員のために支払う費用ですから、個人事業主が自分で利用するための費用は、経費計上できません。家族経営・専従者のみの場合も、同様です。
必要経費についての詳しい内容は、下記をご確認ください。

【確定申告の準備】必要な書類
フリーランスの場合、事業所得を申告するため「確定申告書B(第一表・第二表)」を使います。白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告者は「青色申告決算書」が必要です。
- マイナンバーカード(または個人番号確認書類と身元確認書類)
- 口座情報
電子申告の場合は「マイナンバーカード」または税務署発行の利用者識別番号とパスワードを準備します。
確定申告ソフトを使って確定申告をしよう
フリーランスが確定申告をする際には、確定申告ソフトの使用がおすすめです。基本情報、申告書作成に関する必要事項に答えていくだけで、必要書類が作成できます。電子申告(e-Tax)対応ソフトであれば、印刷や税務署への郵送・持参の手間も省けるため、大変便利です。
フリーランスにとって大切な「確定申告」
会社員やアルバイトの場合、勤務先が年末調整を行ってくれますが、フリーランスの場合、自分で確定申告をしなければなりません。そのためにはまず「事業収入」「事業所得」「必要経費」の考え方を理解することが大切です。
さらに日々の取引記帳や領収書の整理など、やるべきことも多いものの、確定申告ソフトを使うことで、手間は軽減されます。
確定申告のやり方に悩んでいる人は、利用を検討してみることをおすすめします。
文・柚月朋子
フリーランスとしての経験やポイント投資からスタートした経験を活かし、年間200本以上の記事を執筆・監修。投資初心者にわかりやすい記事執筆が目標。